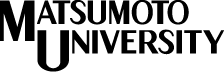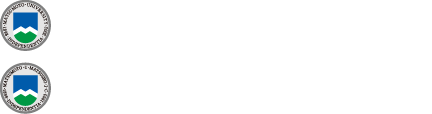新着ニュース
- 教育研究情報
噺家の三遊亭神楽さんをお招きし、特別講義をしていただきました
学校教育学科
准教授 上月 康弘

国語科概論では、これまで数回にわたって伝統的な言語文化の授業においてどんなことが大切なのか、日本語の特徴や機能とは何かということについて、俳句の作成等をもとに考えてきました。今回は伝統的言語文化の学びの締めくくりとして、噺家の三遊亭神楽さんをお呼びし、特別講義ならびに落語の実演をしていただきました。
三遊亭神楽さんを本学にお呼びするのは、2年ぶりです。初めに落語の規則や言葉遣い、演じ方などについてご講義いただきました。その後、落語の演目である「小間物屋政談(こまものやせいだん)」を演じていただきました。
「小間物屋政談」のあらすじは次のとおりです。
京橋の小間物屋・相良屋小四郎が上方で商売中、箱根山で縛られた若狭屋甚兵衛を助けますが、甚兵衛は恩を返すと約束し、小四郎の名刺を受け取りますが、後に死んでしまいます。残った名刺から小四郎が死んだと誤解されてしまい、自宅に残った妻は三五郎と再婚してしまいます。 帰郷した小四郎は妻が再婚をしていることを知り、騒動になる、というお話です。
洗練された神楽さんのご講演で、教室中が大爆笑でした。発話量にするととてつもなく長くなる文章だと思いますが、神楽さんは一切よどみなく、そして様々な登場人物を演じ分けられていました。学生は、「本当に面白かった。」「今までみた落語の中で一番面白かった」などの感想を述べていました。
その後の質問時間では、「なぜ落語家、噺家になったのか。」「真打になるまでにどんな苦労があったのか」など、神楽さんの生き方についての質問があがりました。
神楽さんのお話を聞き、「わざ」を極めるというのは並大抵のことではない、と改めて感じました。一流の世界で活躍している方は、やはり鍛えられ方が違います。そして、落語家の修行や努力は、教師としての力量を向上させる過程と通底する部分があるように感じました。
神楽さんから学んだたくさんのことを、今後に生かしてほしいと思っています。神楽さん、ご多用の中、本当にありがとうございました。


関連する教員