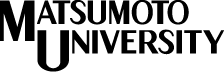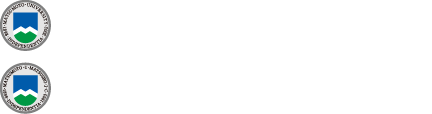新着ニュース
2025/07/07
- 教育研究情報
2025年度前期「総合的な学習の時間の指導法」の特別講義
学校教育学科
教授 澤柿 教淳
2025年度前期「総合的な学習の時間の指導法」において、外部講師をお招きして講義をしていただきました。外部講師のN先生は、これまで優れた実践事例を数多く輩出されており、その取り組みはテレビ等でも取り上げられています。今回の講義では、それらのご実践の舞台裏を学生の皆さんと共有することを通して、授業づくりの醍醐味や、教材研究の奥深さを学ぶことができました。
多くのご実践に共通していることとして、地域の魅力を思いっきり引き出して教材化していること、多方面の人材とつながって共に授業を作り上げるプロセスが充実していること、子ども主体の探究活動の場が多様に想定されていること、などがあると感じられました。ご講義の中ではN先生ご自身の失敗談なども語られていましたが、中でも探究のゴールとして想定していた成果物が予想以上に"立派に"できてしまったことは教師として苦い思い出だ、と語っておられたことはとても印象的でした。
実践に基づいたお話から、参加した学生は多くのことを感じ取っていたようです(以下、事後の感想より抜粋)。
- 今回の講義を通して、地域の魅力を感じた。N先生のように魅力をうまく伝えることができるようになるためには、自ら地域を調べ理解することが前提となると感じた。
- 日常に潜む問題を児童が納得して解決していく過程を構想するのは難しく、その準備には様々な行程があるということを学んだ。
- 実際の動画を見てイメージを掴むことができたし、3〜6年生までの多くの実践事例をテーマ別に知ることができ参考になった。
- 今回紹介された実践事例を見て、「総合的な学習の時間」では、教師と子どもたちだけでなく、地域や地域の人、ゲストティーチャーとの関わりなどが大切だと感じた。
- これまで学習指導要領の内容や指導事例から学んできたが、N先生の講義を通して、より身近なものでどう授業をつくるか、地域の魅力をどう取り上げるとよいのかを勉強できた。
- 地域に密着した事例は、自然豊かな安曇野や松本でも応用できそうだと思った。


関連する教員