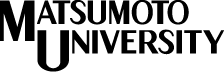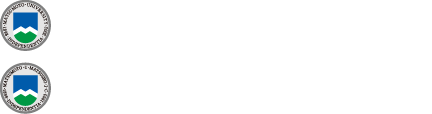新着ニュース
- 教育研究情報
- アウトキャンパス・スタディ事例
平成7年7月豪雨災害(姫川災害)アウトキャンパススタディ
~30年目の節目に被災地を歩く~
松本大学地域防災科学研究所
観光ホスピタリティ学科
教授 入江 さやか
今から30年前の平成7年(1995)年7月11日から12日にかけての豪雨で姫川流域(小谷村・白馬村)に大きな被害が出ました。30年目の節目を前に、6月19日(木)に本学で防災を学ぶ学生が現地を訪れ、姫川沿いで発生した過去の土砂災害と砂防対策などについて学びました。なお、今回のアウトキャンパススタディは、国土交通省北陸地方整備局松本砂防事務所の協力を得て実施しました。
「はじめに砂防ありき」
白馬村に発し、日本海に流れ込む姫川の流域は、急勾配の河川であることに加え、姫川に沿ってほぼ南北に走る糸魚川~静岡構造線のために脆弱で不安定な地質構造になっており、歴史的に多くの土砂災害に見舞われてきました。アウトキャンパススタディでは、まず白馬村の「源太郎砂防堰堤」と「はじめに砂防ありき」の碑を訪れました。この地域は、姫川支流の平川・松川の氾濫や土石流でかつては荒れた土地でしたが、源太郎砂防堰堤をはじめとした砂防工事が進められ、別荘地が開発されるなど、大きく発展しました。「はじめに砂防ありき」の碑は、それを記念して平成3(1991)年に建てられたものです。学生たちは、北陸地方整備局松本砂防事務所の林真一郎所長の解説を聞きながら、現地を見学しました。

源太郎砂防堰堤(奥)で林所長の説明を聞く学生たち

「はじめに砂防ありき」の碑
稗田山崩れを見る
明治44(1911)年、小谷村の稗田山が大崩壊を起こしました。崩壊した土砂は土石流(岩屑なだれ)となって姫川の支川の浦川を流れ下り、姫川との合流点がせき止められて天然ダム(河道閉塞)ができました。浦川下流は厚さ100mもの土砂に埋まり、死者・行方不明は23人にも達しました。翌年の明治45(1912)年7月の豪雨により天然ダムが決壊し、下流の石坂や来馬の集落は壊滅的な被害を受けました。稗田山崩れは静岡県の大谷崩れ、富山県の鳶山崩れとともに「日本三大崩れ」の一つとされています。この日は、浦川の下流から稗田山の崩壊を遠望し、現在も継続している砂防工事の状況を見学しました。

浦川橋から「稗田山崩れ(奥)」を遠望する
蒲原沢土石流災害と慰霊碑
平成8(1996)年12月6日、小谷村と新潟県糸魚川市の境の蒲原沢で、融雪により姫川本川に達する土石流が発生しました。前年の平成7(1995)年7月豪雨による土砂災害の復旧工事にあたっていた作業従事者14人が犠牲となりました。この災害は、砂防工事施工に伴う安 全対策に対して大きな影響を与えた災害でした。現地では、この災害で犠牲となった方々の慰霊碑に学生が献花を行いました。その後、蒲原沢と、災害後に整備された国界橋を見学しました。

蒲原沢土石流災害の慰霊碑に献花する学生たち(左手奥が蒲原沢)
平成7年7月豪雨(姫川水害)とその後の対策
平成7(1995)年7月11日から12日にかけて、梅雨前線による豪雨が長野県北部から新潟県西部を襲い、姫川流域の各地に、地すべり・崩壊・土石流など による土砂災害を多数発生させました。小谷村の平岩地区では、山腹崩壊により発生した土石流が砂防堰堤を乗り越えて流れ下り、国道148号 まで及び、JR大糸線を横切って本川の姫川まで達しました。今回は、松本砂防事務所姫川監督官詰所付近で、当時の被害の状況の説明を受けたあと、質疑応答を行いました。
参加した学生から提出されたレポートには、「実際の現場をみて、どういう状況でどういう災害が起きたのかを考察することで、教室で話を聞くよりインパクトのある学習となった。また、わからないことはすぐに質問できるという環境であることで、疑問がすぐに払拭できるとても有意義な時間になった」「今回実際に災害があった場所を訪れ話を聞いたことで、今まであまり興味がなかった防災について学ばなければと感じるきっかけになった」などの感想が述べられており、意義のあるアウトキャンパススタディとなりました。
なお、アウトキャンパススタディの様子は、6月20日の信濃毎日新聞に掲載されました。
また、7月8日のSBCラジオ番組「Mixxxxx+(ミックスプラス)」内のコーナー「あなたを守る防災知恵袋」(13時30分ごろから)でも放送されました。放送後1週間は、ラジオのネット配信サービスradiko(ラジコ)で聴くことができます。
関連する教員