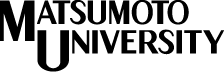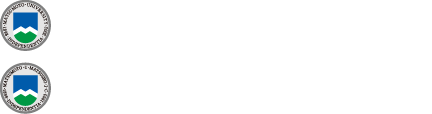新着ニュース
- 教育研究情報
- アウトキャンパス・スタディ事例
教職実践演習(初中等)で、松本市立美術館へアウトキャンパスに行きました
学校教育学科
准教授 上月 康弘

11月27日(木)、図画工作科における鑑賞指導の力量を身に付けるねらいで、松本市立美術館へ見学に行きました。小さな子どもたちは、芸術的作品を目の前にすると、「なんかすごい」「大きい」などの漠然とした感想をもつことが多いです。これは、作品の見方・考え方が充分育っておらず、自ら感じたことを言語化できていないからです。
例えば、一枚の絵に対峙する際にも、筆の使い方、色の塗り方、遠近法、線のタッチの描き分け、対比や非対称などの全体構造など、様々な鑑賞の視点があります。このような視点の内在化は、表現する際の方略としても活用できます。深い鑑賞力を備えることは、それだけ作品を表現する力にもつながり、それはすなわち教師の指導力・力量にもつながっていきます。
今回は、常設展の草間彌生の作品に加え、石井柏亭(はくてい)(1882-1958)の企画展を見学しました。
石井は、幼いころから祖父と父に日本画を学び、わずか10歳で「柏亭」を名乗り作品を展覧会等に出品します。11歳では大正天皇の前で席画を披露するほどの腕前だったそうです。東京大空襲により自宅を焼かれた石井は、戦後、信州の自然に感動したことをきっかけに移住を決意しました。
石井が描く美しい水彩画や油絵が、非常に多く展示されており、とても見ごたえがありました。私が個人的に感銘を受けたのは、学校教育で用いられていた教科書『尋常小学図画』の編纂に携わっていたことです。東京帝国大学の工学部講師としての経験があり、教育者としても活躍した石井の実績が評価され、編纂に選出されたとされています。教科書には、同じ風景でも、線、色、塗り方などの違いによって大きく異なる絵が描けることが提示されていました。確かに、石井の様々な作品を見ると、同じ水彩画や油絵でも多様なタッチや色の塗り方(例えば視点の焦点の中心ははっきり描くが、背景はぼやけたような淡い描き方をしている)を、表現の目的に応じて使い分けている様子が見られました。
学生たちは今後、図画工作科の学習指導要領を基に、鑑賞指導についての要点をまとめていきます。本日の見学で培った学びを、実際の学習指導に生かしていってほしいと思います。


関連する教員